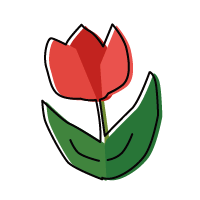【富山の市町村名】95%の人は由来を知らないと思うので調べてみた

どうも、編集長のサクラです。
突然ですが、みなさんは自分の住んでいる市町村の名前の由来をご存じでしょうか?
きっと知らないと思いますし、今後も調べる気にならないでしょう。
わたし自身も自分で「なんでこんなこと調べてるのか?」と自問自答しましたが、その解答は今も得られていません。
ただタイトルの通り、みなさんのために一生懸命調べました。
自分の住んでいるところだけでも見てみてください。

富山市は諸説が3つありまして、以下の通りです。
① 呉羽丘陵が現在の高岡市から外側にあったことから外山(とやま)と呼ばれ、縁起の良い「富山」にしたとする説
② 多くの山が連なり「富める山の国」の意味からとする説
③ この地方は、もともと藤居山(ふじいやま)と呼ばれていたが、富山寺があったことから、富山と呼ばれるようになった説
個人的には2番目がしっくりくるので、2番であってほしいです。
富山市役所展望塔から周りを見渡したらほんと山に囲まれてますからね。

高岡の名前は、前田利長が詩経の「鳳凰鳴矣于彼高岡」(鳳凰鳴けり彼の高き岡に)からとって高岡と名づけたことに由来しています。
つまり、鳳凰が高い丘に向かって鳴いたところに新しくお城を作ったので、そのお城の名前を高岡城とし、地名も高岡市になりました。
こちらは説が明確で、実際に命名の地とされるお寺もあります。

魚津市は、大道、魚堵(おど)→小戸ヶ浦(おどがうら)→小戸(おど)→小津(おづ)と名前が変わっていきました。
出世魚くらいの名前の変化です。
そんで、魚の産地ということで「魚津」となったのが由来になります。
ちなみに、ローマ字表記ではUODU(うおづ)ではなく、UOZU(うおず)なのでここだけ注意です。

黒部市も諸説あります。
① 黒部は山高く、立の真黒に生茂る日の目も見えない辺りをさしていう言葉から出たという説
② 黒部山奥には「ネズコ」と呼ばれる常緑針葉樹が生えており、この別名が黒檜(くろび)と言われていたためという説
③ アイヌ語のクンネベツ「黒(暗)い川」、またはクルベツ「魔の川」からきているという説
1番の説がダーク感があっていいですが、どれにせよ、なんだか恐ろしい名前の由来です。
黒部といえば黒部ダムを思い浮かべる人も多いかと思いますが、こちらもこちらでものすごい大変な歴史があったようですね。

氷見市も諸説あります。
① 「ひみ」は、蝦夷防備の狼煙(のろし)台を置いた土地・「火見」を、火災が頻発したため「氷見」と改称した説
② 立山連峰から昇る朝日を拝む「日見」とする説
③ 海をへだてて、立山連峰の万年雪が見えるところだから氷見と言った説
火災が頻発していたとは意外ですね。
氷見市には、くるみ火の神社という火という名のついた場所もあるので、あながち間違っていないかもしれません。

「となみ」は、古くは「利波評」という感じで言われていました。
古代の部民・鳥取部の居住地で、山々を越えてくる鳥を「鳥網(となみ)」を張って捕らえた土地とする説があります。
なぜ名前を砺波に変えたのかの明確な由来はわかりませんが、砺が「磨く」って意味で、波は木々が波のように動くことから当て字としたと考えられます。

南砺の由来は、古来砺波郡の南部を指すからです。
つまり、砺波の南になるからというわかりやすい名前ですね。
ただ、砺波市の名前の由来が明確ではないので、そこだけ少し引っかかります。
砺波市と言えば五箇山が有名なのですが、こちらも五箇山とは関係ありませんでした。

射水市は、「万葉集」に「伊美豆」・「伊美都」と書いてあったことから名付けられました。
「いみつ」は、「出ずる水」の意で、「川口」又は二上山の「湧き水」を示したとする説があります。
出水市でよかったのではないかと思ったのですが、やっぱり勢いがほしくて射水市にしたのでしょう。うん、そうですよね。別に卑猥とかではありません。

小矢部市には、上流に小矢部という村があったことに由来して、まず小矢部川と名前が付きました。
そして、小矢部川が流れていることから小矢部市と名前が付きました。
谷間の村のことを昔、谷部(やべ)と読んでおり、特に小さい谷部だったからかと考えられます。

滑川市には2つの説があります。
① 日本海の怒濤が河川に入り込むことから「波入川(なみいりかわ)」から転じた説
② 当地を流れる川の川底が苔などで滑ることからとする説
つまり、波入川という地名でしたが、よく滑るから滑川に変えたんじゃないかと考えられます。
かなり安易な名前の付け方ですが、日本人の名字も安易に付けられているのでそんなもんですね。

日本三霊山の一つ立山に因む町名です。
立山の山の由来は、日本を作り終えた神が天界に戻る際に踏み台代わりに足をかけて立った山だから「たちやま」という説があります。
これには昔から歴史があって、かなりの正確性がありそうです。

入善町には3つの諸説があります。
① 「源平盛衰記」に入善小太郎安家の名から来ている説
② 「にゅうぜん」は、仏教用語「善に入る」や「入禅」の換え字とする説
③ 布施(黒部市)の人々が新しく開墾した土地・「新布施(にいふせ)」が転訛した説
んー、どれもしっくりこない感じですが、新布施を仏教用語に変えた説が合ってるような気がします。

1954年、一町六村の合併の際、北アルプス最北端に位置する名峰・朝日岳に因んで名付けられた新町名です。
朝日岳は最初に陽光を受ける山の意味なので、新しいので正解ですね。
めちゃくちゃ普通でしたが、朝日町のヒスイ海岸は全国でも珍しいスポットです。

この地域では、古くから山岳信仰の山「剱岳」の道中で、三の付く日に三日市が開かれていました。
その土地の上で「上の市」というのが開かれたことから「上市野」と称するようになったといいます。
そこから上市と呼ばれるようになったというわけなので、少しややこしいですね。

最後は、最強の村である舟橋ですね。
こちらは室町時代に仏生寺城主が城の堀に舟を連ねて橋を架けたことに由来していて、かなり歴史があります。
由来もさることながら、今後もここだけはずっと村であったほしいです。
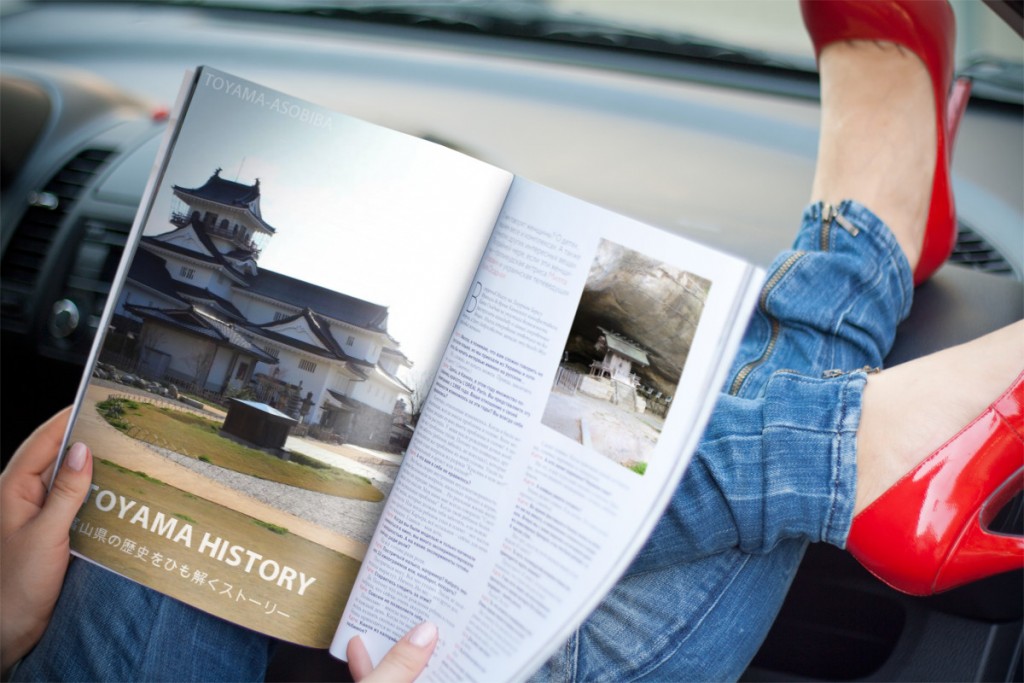
ということで、自分の住んでいる場所の名前の由来がわかったでしょうか?
まぁ諸説あるので本当かどうかはわかりませんし、わからなくていい気がします。
それではわたしは、上市町が市に進化して上市市になることを祈って今後も少子化対策を頑張っていきます!
また舟橋村がどのように生き残ってきたか、昔の富山県はどんな歴史があったかをまとめた記事もありますので、こちらも参考にしてみてください。